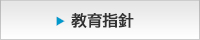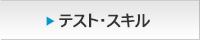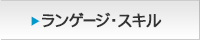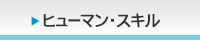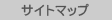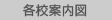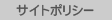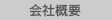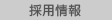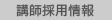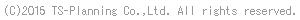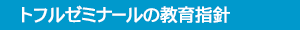

1.思考のための英語力

コトバだけが思考の道具ではありません。現代においてむしろ私たちは、様々なイメージによって外界を捉え、選択し、判断しています。しかし、見たり聞いたりしたら分かるということは、直感的で統一的な把握が可能である一方で、ものごとを分析し、体系的に積み上げていくような本格的な思考の道具としては、やはりコトバに勝るものはないと考えられます。
外国語としての英語を学ぶことは、‘母語の相対化’を通じて‘思考の道具としての言語能力’増強に少なからず寄与するものです。‘母語の相対化’とは、自分が空気のように付き合っている母語を少し突き放し、「この自分のコトバは、私の考えや行動にどう影響しているのだろうか」と、立ち止まって反省してみることです。
とりわけ、ともすれば「曖昧さ」が美徳とされ、「以心伝心」が尊ばれる日本語文化圏において、外国語である英語を学ぶことは、母語による思考活動を分析的に捉え、論理的な表現力を得るために必須でしょう。
単語の語源に込められた生活感覚と伝統に触れ、センテンス構造に隠れたロジックを発見し、パラグラフ構成のあり方の中に世界観を発見する―それは必然的に母語と母語による思考方法を見つめ直し、思考の道具としてのコトバの使用を意識化することになります。