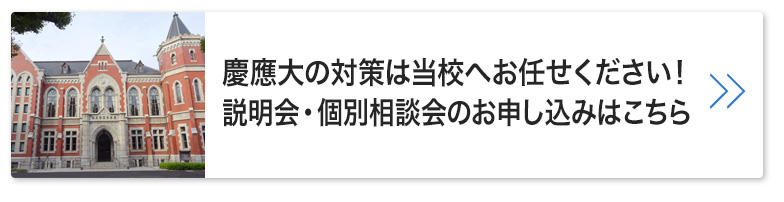慶應義塾大学のイメージというと、「政治家」や「プロ野球選手」、「アナウンサー」など特定の人物像を思い描く人、あるいはコンピューターが進んでいるなどの設備面を挙げる人、あるいは実務力が身につくようなインターンシップ制度などのカリキュラムを思い浮かべる人など、様々ではないでしょうか。慶應義塾大学はどのような大学なのでしょうか。あえて言えば、それらのイメージすべてを含めた全体が、慶應義塾大学そのものなのです。日本有数の総合大学として、教育の原点をきちんと踏まえ、さまざまな設備とすぐれたカリキュラムを提供しているその結果が、数多くの著名人を輩出しているのです。
入試には一般選抜、総合型・学校推薦型選抜があります。 このページでは、慶應大学の合格に必要なことから、慶應大学の教育の特徴まで説明します。

慶應大学は入試改革という点では大きな変更はありませんでしたが、元々高い難易度の英語試験を実施してきたことや、小論文・論述力試験で思考力・表現力を要求してきたことも理由だと考えられます。
実際の入試問題においては、いずれの科目も各学部の求める力が明確であり、英語や小論文は学部の特色が色濃く反映されたものと言えるでしょう。学部ごとに出題形式・テーマや傾向は異なりますが、学部を問わず難易度の高さと配点の高さから、英語が最も合否を左右する大学と言えます。また、他難関大学と比較しても、英語の配点比率の高さは特徴の一つです。配点が高い分、英語力を武器にできれば合格の可能性を高められる大学とも言えます。
年度や入試方式、学科により異なりますが、過去の倍率は以下の通りとなっています。
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||
| 学部 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 文-自主応募制 | 260 | 121 | 2.1 | 275 | 129 | 2.1 | 358 | 127 | 2.8 |
| 法-法律-FIT-A方式 | 221 | 41 | 5.4 | 214 | 45 | 4.8 | 248 | 46 | 5.4 |
| 法-法律-FIT-B方式 | 144 | 63 | 2.3 | 142 | 63 | 2.3 | 175 | 66 | 2.7 |
| 法-法律-IB方式 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.0 |
| 法-政治-FIT-A方式 | 231 | 43 | 5.4 | 258 | 43 | 6.0 | 281 | 46 | 6.1 |
| 法-政治-FIT-B方式 | 149 | 66 | 2.3 | 178 | 62 | 2.9 | 177 | 64 | 2.8 |
| 法-政治-FIT-IB方式 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 理工-分野志向型 | 8 | 2 | 4.0 | - | - | - | 10 | 4 | 2.5 |
| 総合政策-夏秋AO | 664 | 102 | 6.5 | 712 | 121 | 5.9 | 759 | 129 | 5.9 |
| 環境情報-夏秋AO | 533 | 107 | 5.0 | 582 | 129 | 4.5 | 615 | 128 | 4.8 |
| 看護医療-AO-A方式 | 64 | 4 | 16.0 | 48 | 3 | 16.0 | 55 | 8 | 6.9 |
| 看護医療-AO-B方式 | 36 | 4 | 9.0 | 33 | 3 | 11.0 | 26 | 6 | 4.3 |
| 合計 | 2,313 | 555 | 4.2 | 2,445 | 600 | 4.1 | 2,706 | 625 | 4.3 |
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||
| 学部 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 文 | 3,731 | 1,172 | 3.2 | 3,796 | 1,196 | 3.2 | 4,261 | 1,279 | 3.3 |
| 経済-A方式 | 3,286 | 1,102 | 3.0 | 3,699 | 1,150 | 3.2 | 3,911 | 1,017 | 3.8 |
| 経済-B方式 | 2,015 | 480 | 4.2 | 1,691 | 433 | 3.9 | 1,977 | 391 | 5.1 |
| 法-法律 | 1,569 | 352 | 4.5 | 1,466 | 380 | 3.9 | 1,626 | 407 | 4.0 |
| 法-政治 | 1246 | 329 | 3.8 | 1,212 | 324 | 3.7 | 1184 | 367 | 3.2 |
| 商-A方式 | 3,947 | 1,621 | 2.4 | 4,354 | 1,669 | 2.6 | 4,473 | 1,640 | 2.7 |
| 商-B方式 | 2,404 | 382 | 6.3 | 2,343 | 385 | 6.1 | 2,811 | 403 | 7.0 |
| 医 | 1,219 | 168 | 7.3 | 1,270 | 169 | 7.5 | 1,284 | 177 | 7.3 |
| 理工 | 7,627 | 2,452 | 3.1 | 7,747 | 2,495 | 3.1 | 8,139 | 2,728 | 3.0 |
| 総合政策 | 2,574 | 441 | 5.8 | 2,351 | 433 | 5.4 | 2,635 | 432 | 6.1 |
| 環境情報 | 2,319 | 362 | 6.4 | 2,048 | 380 | 5.4 | 2,169 | 376 | 5.8 |
| 看護医療 | 500 | 163 | 3.1 | 465 | 182 | 2.6 | 507 | 150 | 3.4 |
| 薬-薬 | 1314 | 306 | 4.3 | 1,252 | 317 | 3.9 | 1073 | 327 | 3.3 |
| 薬-薬科 | 824 | 195 | 4.2 | 815 | 290 | 2.8 | 835 | 262 | 3.2 |
| 合計 | 34,575 | 9,525 | 3.6 | 34,509 | 9,803 | 3.5 | 36,885 | 9,956 | 3.7 |
慶應大の英語は私大最難関の一つと言われ、長文読解の分量も多く、語彙レベルも高いものです。さらに、何と言っても出題される問題の形式が多様なことが特徴的です。空所補充問題や内容把握問題を含む長文読解問題はもちろん、文法問題と単語問題、学部によっては会話問題や英作文問題がこれに加わります。
◆どの学部においても英語の配点が高い!
文学部48%、経済学部48%、商学部50%、法学部50%、総合政策学部50%、環境情報学部50%、看護医療学部60%、理工学部30%、医学部30%、薬学部29%
*総合政策・環境情報学部は①方式の場合
◆文学部で英検利用が可能!
外国語の科目として「英語(外部試験利用)」の選択が可能。基準は英検CSE2500以上で合否は問われません。当日の英語試験が不要になるメリットは大きいと言えます。併願大学の対策にもつながるため、早期の準備が有効です。
*英検対策の詳細はこちらをご参照ください。
慶應大学は現代文・古文・漢文の出題をしない代わりに小論文を導入しています。課題文は長く難度の高いものであり、読解力も要求されるものとなっています。
*法学部は「論述力」、商学部は「論文テスト」という名称・内容です。
総合型・学校推薦型選抜、一般選抜いずれにおいても、学部ごとの欲しい人材像に合ったテーマが出題される点で、特に大学・学部のアドミッション・ポリシーの研究が重要です。
一般選抜においては、英語、小論文、選択科目いずれにおいても、各学部らしさが反映された内容になっています。

慶應大の合格に向け、高3・高卒生向けの実戦的な対策と、高2・高1生向けの早期準備のための対策があります。
トフルゼミナールは、それぞれに合わせた対策講座を提供しています。
受験生向けの授業は基礎力・総合力を伸ばすためのものから、慶應大専用対策の講座まで幅広いラインナップを揃えています。英語以外にも、小論文、歴史、数学、情報の対策講座があります。 部活で忙しい方や近くに校舎がない方も安心してください!
授業は通学型 / オンデマンドから選ぶことができます。
以下は、対策講座の例です。
この講座ではどんな場面にも通用するランゲージ・スキルとしての読解力、それを支えるヒューマン・スキル(思考と知識)を鍛えます。多様な性格を持つ英文のそれぞれの読み方に習熟できるように、パッセージは以下の3つのタイプに分かれています。
Type 1=Academic:教科書・TOEFL Test・百科事典に典型的に見られるPassageの読解を目指す。
Type 2=Critical:学術的な評論・国内難関大学の長文に典型的に見られるPassageの読解を目指す。
Type 3=Descriptive/Diverse:描写的・表現的な性格を有するPassage(物語・ジャーナリズムなど)の読解を目指す。
また、それぞれの英文のタイプに適合したnotes(注解)、qusetions、review(復習)のパートがあり、reviewにはReadingとListeningの両方の強化に繋がる要素が含まれています。
さらに、すべての英語力の基礎となる語彙力を高めるためのVocabulary、また英文の文化的背景に目を向けさせるためのExpanding your Horizonsというコラムが各レッスンにあります。
英語の4技能(読む・書く・聴く・話す)すべての基盤となる文法・語法力と、それに基づく「書く」技能を養成することを目標とした科目です。Lev.3までの知識の習得を前提として、Lev.4では大学受験やTOEFL Testなどの英語資格の試験対策につながる実戦的な問題演習を多く取り入れます。
Grammarのパートは、各レッスンに一定の文法的テーマと項目を設け、年間を通して英文法の全体が網羅されます。Writingのパートでは、各レッスンの文法項目の理解に基づくsentenceレベルの英作のほか、大学受験やTOEFL Testで重要となるエッセイライティング(意見・自由英作文)の導入的演習を行います。
正しい音声の習得を徹底し、より実践的なリスニング力およびその助けともなるスピーキング力の育成を目指します。
Lev.3/Lev.4では、これまでのLev.1/Lev.2と違って、スピーキングよりリスニングの比重が高くなります。具体的には、大学受験のリスニング、英語資格試験のリスニング・スピーキング学習に移行するために必要不可欠な能力を育成します。
大学受験においてもリスニングの重要性は高まっており、英検、ELTiS、TEAP、TOEFL/TOEIC L&R Test、IELTSなど各種資格試験の重要性も増しています。いずれの対策を行うにしても、この講座がその準備の土台となります。
英検、TEAP、TOEFL、IELTSなど英語資格試験の対策講座があります。現在の英語力や志望校、方式に合わせて選ぶことができます。
グローバル社会におけるキーワードについて、歴史的背景や関連する事柄を学ぶことで社会的な視野を育成します。さまざまなテーマごとに、①歴史を振り返り、②現在を確認して、③2050年がどうなっているかを構想します。論文やエッセイ対策にも有効です。
アカデミックな文章の読解、図表データの読み取り、根拠を持った主張構築などの練習を通して、そうした日本語の「コア(核)」となる技能を磨くとともに、何のために大学に進学するのかを考える機会を設け「現代文」「小論文」や、総合型・学校推薦型選抜の準備を行います。
「社会的な問題に対して知的好奇心を持って関心を持とうとする積極性」「そして自分から考え、自分の考えをまとめ、意見として述べる」「さらに自己をアピールできる表現力を持つ」ことを養成するための講座です。総合型・学校推薦型選抜での自己アピールや、ディスカッション形式の面接および小論文対策の基礎づくりに有効な講座です。
実際に出題された読解・文法・語法問題に取り組み、早稲田大・慶應大突破のために必要な英語力を体感し、合格に向けて一歩リードするための高2生向け講座です。
出題分野、傾向、形式別に構成されたテキストを使用し、問題分析を行い、早稲田大・慶應大で求められる英語力はどのようなものなのかを「しっかり知る」ための高2生向け講座です。
以下は、対策講座の例です。
⾧文読解力をつける3要素、「効率的かつ正確に内容を把握する技術を知る」「多くの⾧文に触れセンスを磨く」「的確な問題解法を身につける」を、総合的に高めることが目的です。フレーズ・センテンス・パラグラフ・パッセージという英文のそれぞれのレベルに合致した「読解のメソッド」を身につけ、正確で効率的な⾧文読解のための技術を体系的に習得します。
春学期では、英文法項目を体系的にまとめた問題形式のテキストで、英文法の全体像がみえるように解説します。基本的文法項目の理解に加え、弱点や誤りやすい事項に関しての完全な整理を行います。
秋学期では、早慶上智を含めた難関大学対策用の問題演習により、幅広い応用力を養成するとともに、いかなる形式の問題や難問にも対応できるよう指導します。
英検、TEAP、TOEFL、IELTSなど英語資格試験の対策講座があります。現在の英語力や志望校、方式に合わせて選ぶことができます。
正しい音声の習得を徹底し、より実践的なリスニング力およびその助けともなるスピーキング力の育成を目指します。大学受験のリスニング、TOEFL Testのリスニング・スピーキング学習に移行するために必要不可欠な英語能力を育成します。
総合型・学校推薦型選抜対策の基本講座です。主に自己推薦書・志望理由書などの書類作成や面接準備を行います。 入試でキーになる要素は、自己を社会の中に位置づけて経験や将来像を明確なイメージにまとめる自己把握力と、そのイメージを伝えるためのコミュニケーション能力です。高2冬期からスタートし、文章作成練習を通して表現のスキルアップを図りながら志望動機を明確にしていきます。夏期から秋学期にかけてはその成果を提出書類にまとめあげます。
総合型・学校推薦型選抜の筆記試験に対応した小論文講座です。前半では句読点や原稿マスの使い方などの書き方の基礎をはじめ、どのように「考える」か、ということを主眼に学習を進め、担当講師による徹底的な添削で少人数制ゼミならではのきめ細かい指導をしていきます。小論文の基本から説明してレベルアップを図り、後半は実践的な問題練習を行うとともに、大学学部系統別に必要となる知識インプットの方法をアドバイスします。
慶應は学部により傾向は異なりますが、授業内で個々に対応し、目標に向けての知識を確かなものにします。春学期は各学部の問題の中でも普遍的なテーマを扱ったものを取り上げ、課題文からの論点の取り出し方や主張の論理構成などを指導します。秋学期には学部ごとに必要となる背景知識の解説や答案での論点の深め方へと進み、直前期に各学部特有の問題を個別に指導します。
ハイレベルな社会科学系小論文のために、社会問題に関する知識や背景の理解のインプット講座です。課題文を読んで理解度をチェックし、論述問題に挑戦します。
社会科学系学部の総合型・学校推薦型選抜のための早期対策。政治・法律・経済・社会などに関する課題文を読んで、グループ討論や小論文の作成を行います。
特に難関大学の正誤問題には正確な知識が必要となるため、正確な知識と自信が身につくように指導します。春学期は原始・古代から織豊政権まで、秋学期は江戸時代から現代までを扱い、直前期には、頻出のテーマ史を中心としたテストゼミが用意されおり効果的に即戦力をつけることができます。
春学期は、人類の誕生から始めて前近代までを終わらせ、秋学期にはルネッサンス以降から近現代を扱います。早慶上智やトップ国公立などの最難関校の入試問題に対応できるよう必要な知識の完全習得を目指します。直前期は、テストゼミ形式で総合力確認と文化史の復習を行います。
過去に出題された問題の演習を通して基本的な公式から学習していきます。共通テストの数学は、助詞や接続詞に着目することが大切で、重要なヒントになっていることが多いのです. 年度によっては解きにくい問題が出されることもありますが、多くの問題を解いていけば動揺しないようになります。
近年の慶應大(法・経・商)の入試問題の傾向を徹底分析し、その問題演習を通じて適切な解答を導く術を習得することを目標とします。主に読解問題を中心として演習を行いますが、文法・語法および語彙問題の対策も合わせて行います。
慶應大(環境情報・総合政策)の各学部で出題される問題は、従来の大学入試問題の枠組みと異なり、英米で行われているテスト形式を参考とした出題傾向になっています。この講座では、過去に出題された長文空所補充問題、内容把握問題に徹底的な傾向分析を加え、両学部合格のための対策を講義します。
2次選考の講義論文試審査・口頭試問までを徹底的に指導します。授業は基本的に少人数クラスで行い、講師による個別のアドバイスに加えて、実際の試験形式に沿った模擬練習を行います。また、別途オプショナルで個別指導・人間力養成講座を受講することで、出願書類である活動報告書の指導・添削も可能です。
慶應義塾大の文学部自主応募推薦は、総合考査と呼ばれる小論文形式のテストがあり、評論文に対する理解力とそれに対する文章表現力、さらには和文英訳力までが試され合否が決まります。この講座では、思想・芸術論・文学論などの高度に抽象的な課題文に対し、どのように的確に論述するかを最終チェックするほか、とくに抽象的な表現の英訳についても解説します。
法・経・商各学部の問題傾向を徹底分析し、解法を検討するとともに、予想問題も含めて慶應受験に完璧に備えます。
出題の多さ、難度の高さから非常に高度な英文読解力が要求される慶應大のSFC。講座では両学部で共通して出題される空所補充問題と選択式の読解問題(内容把握)に対する総合的なアプローチを、オリジナル問題を用いて行います。
文法・語法の知識の差が、英語重視の難関大で合否を分けるケースが多々あります。この講座では、文法問題および細かい語法や類義語のニュアンスなどの整理を行い、入試レベルでは最高難度の文法をマスターします。





僕は第一希望だった慶應大学に合格することができましたが、それは英語の力によるところが大きいと思います。各大学の配点をみても英語を重視するところが多いですし、やはり私立文系の人にとって英語は受験の「鍵」になるのではないでしょうか。
一つアドバイスをさせてもらうと、目標を持ち続けることです。ここで言う目標は偏差値でもいいし、ライバルに負けないといったのでも構いません。さらに言うと、目標は短期的なものの方がいいです。
長期的な大きな目標も大事ですが、いまいちピンと来ないものです。そして、目標を下げないでください。一回下げると、また下げてしまう可能性もあるし、なにより目標を下げることは自分を信じていないということなのですから。
私は、高校2年生の10月からトフルゼミナールに入学したのですが、初めの英語の授業でクラスのみんなと授業内容のレベルの高さに驚きました。しかし、そのおかげでそれまで以上に英語に真剣に取り組むようになりました。 慶応文学部を意識して小論文対策を本格的に始めたのは高校3年生の夏休みからです。
私はもともと一般入試で慶應大学を受験するつもりで小論文を書き始めたのですが、書いていくうちに自分の知識も深まり楽しいと感じるようになって、評定が足りていたこともあり自主応募制推薦も視野に入れるようになりました。
トフルゼミナールで受講した慶應文学部自主応募制推薦入試ゼミは、慶應文学部の問題に特化していて集中的に対策ができたので、非常に有意義でした。そこから小論文のコツもつかめ、ハイペースで書けるようになりました。
一般受験のための勉強との両立は正直辛かったですが、どちらの成績も維持しようとすることで逆にモチベーションが上がりました。またトフルゼミナールでは、どちらの対策も併行してサポートしてもらえたので、安心して対策ができたと思います。
小論文で培った様々な知識はこの先もずっと役立つことばかりなので、挑戦して本当によかったです。
英作文は定期的に書くようにしてトフルの先生に添削していただきました。常に自分のレベルよりワンランク高い授業を取り、ついていけるように必死に勉強しました。トフルでは難しい問題にたくさんチャレンジできたので、本番の試験は比較的スムーズにとくことが出来たと感じました。現在の自分の位置など気にせずに常に高い志望校を目指して努力する姿勢が何より大切だと思います。
1年間の留学から帰国して、受験の知識も学力も全くない状態でトフルを紹介され、まず入会テストを受けて入りました。トフルのスタッフの方々と相談をして、受験プランを作って頑張ったおかげでうまくいって良かったです。
トフルの人は皆フレンドリーで受験で出来た友達も増えてよかった。留学の英語が役に立ってよかった。
Wish you all a lot of luck!
SATでまわりの人達の英語スキルの高さに刺激されながら(もちろんTOEFL®でも)、「がんばらなければ!」という気持ちになって勉強できたことがすごく自分のためになったなぁと思いました。他の塾ではできないような話し合い形式の授業は気楽に、眠くならずに勉強できて、本当に楽しかったです。本当に、どうもありがとうございました!!
また、スタッフの方々が親身になって後ろから支えて下さり、なんでも相談できるような空気を作ってくれたことが、やはり大きな心の支えになりました。特に、よくグチを辛抱強く聞いて下さったカウンセラーさん、毎回毎回申し訳ありませんでした&本当にお世話になりました、ありがとうございました。
更に、授業でもエッセイでもいつもお世話になった先生のご恩は忘れません。淡々としているけれどもすごく親身になってバックアップしてくれて、本当に先生がいなければ合格できなかったと思います。ありがとうございます!
- 他の体験談も見る
-
E.H.(東京都私立頌栄女子学院高校):法学部
トフルで勉強できて本当に良かったと思います。スタッフの人達の優しさが本当にうれしかったです。たくさん友達もできて、志望校にも合格できてとても良かったです。
あまり深く勉強法や講座の数など気にすることなく目の前にあるものから取り組んで終わらせていくのが一番良いと思います。
私は毎日終えることのできないスケジュールを作っていましたが、ちゃんと計画をたててやらなくてはいけないものを自覚できたのが良い方法だったと思います。
A.K.(東京都私立東京女学館高校):文学部トフルの英語はレベルが高く、毎週授業の予習に苦労しました。特に夏休みに受講した授業はとても難しく半泣きになりながら予習・復習をしましたが、レベルの高い長文に日々触れていたため入試問題はどれも簡単に思えました。
また、トフルは少人数制のため先生が授業中生徒をどんどん当てるので気を抜くことなく集中して授業をうけることが出来ました。
トフルのおかげで英語の読解力に力がつき、無事第一志望に合格することができました。
M.K.(東京都私立東京女学館高校):文学部トフルゼミナールは私の友達の英語が出来る子が通っていて、良さそうだなと思って入りました。とても、アットホームな雰囲気で楽しく勉強ができました。英語の成績が少しずつ伸びたのもトフルのお陰だと思います。
トフルの授業で良かったのは、少人数制なので先生との距離が近く、分からないこところがあったらすぐ質問できるところ、そしてテキストに載っている問題が良かったところです。
私は特に予習に時間をかけました。テキストの問題は難しかったので十分に予習をして授業に臨む必要がありました。予習に時間をかけると、授業も自然と集中して聞き、分かった点、分からない点がはっきりし、何が自分に足りないのかを知ることができます。分からなかったら、すぐ先生に質問をしました。復習は帰りの電車で、テキストの書き込みの無い英文だけを読み、スラスラ理解しながら読めるか、あるいはスラスラ文法の問題を解けるか…を確かめて、家に帰って“スラスラ出来なかった部分”をチェックしました。
…このような感じで私は英語をトフルで勉強しました。
トフルで良かった点(授業以外で)は、スタッフの方々サポートです。あんなに親身になって色々なことを聞いてくれたり、話してくれたり…つまり相談に乗ってくれる(笑)塾は他に無いのでは…というぐらいです。本当にスタッフの方々にはお世話になりました。(特に松井さん!ありがとうございました!!)
AO入試に失敗したり、辛いこともたくさんありましたが、結果的に第一志望の大学・学部に合格することが出来ました。これもトフルの先生方、教科書、スタッフの方々のお陰です。本当に本当にありがとうございました。大学でも頑張ります☆
R.M.(東京都私立桐朋高校):商学部僕は高三の夏まで野球をしていました。それまでコツコツ勉強していなかったので、引退した頃の英語力はかなりひどいものでした。そして、基礎力が身についていないのに、その夏からの半年、過去問ばかりを解いて、その出来に一喜一憂する日々を送りました。
現役時の受験はすべて失敗。受験が甘くないことを痛感しました。英語も得意科目にしなければ、どこの大学も受からないと思い、浪人時は英語に強いトフルにお世話になろうと決めました。
トフルの授業で扱う英語長文は難しいものばかりで、正直初めは周りについていくだけでいっぱいいっぱいでした。でも平行して基礎的な文法、構文といった基礎力が固まっていったので、徐々に英文を読むコツが掴めるようになりました。どんどん力がつくのを実感し、結果的に得点源になりました。
自分の持っている力を把握することが受験に大切なことだと思います。今、自分に何が足りないのか、それを補うために何を勉強すればいいのか、を知り、効率よく勉強できたおかげで望んでいた大学に合格できたと思います。
トフルでの1年を無駄にしないように大学でもさらに英語に磨きをかけたいと思います。ありがとうございました。
R.M.(東京都私立国際基督教高校):経済学部私は慶應義塾大学の商学部を数学を使うA方式で受けました。数学の個別指導の先生には2年生から教わりました。個別指導なので普通の授業では聞けないような質問も気軽に聞くことができました。先生はその質問に丁寧に答えてくれました。最初はセンターの問題もほとんど解けなかったのですが、慶應に合格できるだけのレベルまで上げることが出来ました。本当にありがとうございました。
M.G.(千葉県私立東邦大東邦高校):文学部私はトフルゼミナールでは英語のみの受講でしたが、英語が最後に一番伸びたので、トフルに入ってよかったとおもっています。あきらめずに最後まで頑張ってよかったです。ありがとうございました。
T.U.(私立スイス公文高校):総合政策学部私はトフルゼミナールで大学探しの段階からお世話になりました。いくつかの行きたい大学の候補や、将来やりたい職業などのイメージは元々持っていましたが、かなり漠然としたものでした。初めてトフルゼミナールに相談に行った際、担当の方が何時間もかけて私の気になる大学の情報や対策の話をしてくださり、安心して入会を決めました。
私の取っていた個人レッスンでは、自分のやりたいことは何なのか、自分の持つ強みとは何なのかを先生と一対一で見つけるところからはじまります。その後、それを徐々に大学の志望理由書に当てはめていくという流れで、志望理由書の添削から面接の対策まで全てサポートして頂けました。レッスンが合格に不可欠だったことは言うまでもありませんが、その他にも、自分がその大学に何のために行くのか、将来何をしたいのかなど、大学に合格した後のその先に繋がるものを見つけることができました。
受験生活はとても厳しい道のりです。ですが、私は適切なサポートによって、他の受験生よりずいぶん有利に進めることができたと思います。
M.T.(東京都私立大妻多摩高校):法学部私がトフルの授業を受け始めたのは、高3の春でした。トフルの英語は少人数の授業で、毎回必ず当てられるため、ただなんとなく授業を受けるということがなく、授業時間にしっかり集中することができました。
私はもともと英語は得意なほうでしたが、トフルの模試はレベルが高いので、油断せずに常に高いレベルを目指すことが出来ました。トフルで教わる英語は、受験英語のレベルを超えているので、授業をしっかりこなせば余裕を持って試験本番に挑むことが出来るし、受験勉強が終わってからも、トフルで身につけた英語は充分に活かすことができます。
トフルの先生やチューター、スタッフの方々は、気さくに話かけてくださる方ばかりで、アットホームな雰囲気がトフルの最大の特徴だと思います。わからないことや困ったことがあるとすぐに親身になって相談にのってくださるし、授業以外のフォローもしっかりしているとても信頼できる予備校でした。
M.N.(東京都国立筑波大学附属高校):文学部トフルゼミナールには、高1の冬から通っていました。少人数制の授業で、いつも集中していなければならない環境がありました。また、教材の英語のレベルがとても高かったので、毎回充実した時間をすごすことができました。トフルで高3まで勉強したおかげで、私にとって英語は単なる得点科目でなく、自信の持てる得点源となりました。
高3から国語、日本史、小論文もトフルで講座を受講しました。英語は安定するようになっていたので、バランスを見て他の科目の勉強ができよかったと思います。
大学受験は地道な努力なので、先が見えず不安になることもありましたが、トフルの先生方やスタッフの皆さんに幾度も励ましていただき、前向きに頑張ることができました。第一志望に合格したときのうれしさは忘れられません。受験で努力したことを大学生活に活かせたらいいなと思っています。本当にお世話になりました。
R.N.(東京都国立筑波大学附属高校):法学部私は高1のときからトフルに通っていました。トフルの少人数制が気に入っていました。あと少人数制なので、クラス全員が仲良くなれたので、塾の授業も休み時間も楽しく過ごすことができました。スタッフの方々や先生方も親しみやすく、いつでも気軽に相談できました。
高1のときは自分であまり勉強しませんでしたが、トフルの英語の授業の内容がとても充実していたので、その予習、復習だけでも充分でした。高2のときは、学校で世界史をやっていなかったので、高3からでは間に合わないと思い、講習で世界史の授業をとっていました。そのおかげで世界史は早いうちから好きになりました。
3年間を通じて、先生に困ったらすぐに相談していたことが結果的に良かったのだと思います。トフルにはほんとにお世話になりました。トフルで良かったです。
M.T.(埼玉県私立浦和明の星高校):法学部私は、受験勉強を意識しだした高2の3学期にトフルゼミナールに入りました。もともと私立文系を志望していたので、入試での配点が高く、差がつきやすい英語をとにかく伸ばしたかったからです。
トフルの教材はとにかくレベルが高く、量も多かったので予習、復習は大変でした。1学期、2学期は学校の授業の復習とトフルの予習、復習だけで終わってしまい不安でしたが、数冊の教材を徹底的にやり込んだことがかえって良かったのだと思います。
雰囲気もアットホームで不安になった時は先生方や受付の方々が相談にのってくださり、自信をもって受験を乗り切ることができました。
M.I.(千葉県私立市川高校):経済学部トフルに入って感心したことは、受付の人達がいつも挨拶してくれてアットホームなところと、少人数制なので授業に集中でき、講師との距離が近くに感じました。疑問点や細かいことも積極的に質問できました。3年生の10月の模試では偏差値74をマークし、それを支えに本番では緊張せずに受けられました。
H.K.(東京都私立成蹊高校):法学部私は、受験か内部進学でダラダラと悩んだまま高2の秋になんとなくトフルに入りました。しかし、入ってみると授業では必ずと言っていいほどあてられるし、予習なしではもちろんついていけないし、“なんとなく”だけでは受験など無理なことがわかりました。
でも、そのほどよい緊張感がかえって受験を意識できてトフルでしっかりやれば受験に勝てると思いました。テキストが難しくても面白い先生方が丁寧に教えてくれます。
何度もくじけそうになりながらトフルで頑張って良かったと今、本当に思います。
A.M.(東京都私立立教女学院高校):法学部授業を受けて帰るだけでクタクタになり、一年間続けられるのか不安になりました。でも、そんな時こそトフルの良さを実感しました。先生方やスタッフの方は私達の愚痴を聞いてくれたり、いつも支えになってくれました。トフルは生徒・教師・スタッフとの距離がとても近く、勉強面だけでなく精神面のケアも万全だと思います。
A.Y.(東京都私立頌栄女子学院高校):経済学部トフルゼミナールの授業は本当に辛かったです。特に読解は予習と復習が大変です。それ以上に授業中が一番大変でした。100分の授業は、一人で勉強した3時間・4時間にも値すると思います。予習・復習は手を抜く事は簡単ですが、それを怠らず地道にこつこつ努力すれば、必ず英語の成績は上がると断言できます。
K.M.(東京都私立世田谷学園高校):環境情報学部私が受験勉強を意識し始めたのは、高2の夏からでした。当時、受験について右も左もわからなかった私でしたが、スタッフの心温まるケアや先生方とのカウンセリングによって、3年生になったころにはよいスタートが迎えられたと思っています。
受験勉強中は学校、家、トフルを行き来することが多く、宿題や予習を先生に見て貰うことで、自分の間違いに気づくという勉強法をとっていました。そのため、自分が納得するまで質問を続ける私に、この塾は適していたと思います。
また、スランプで立ち直れなかった時や、試験直前の焦燥感に駆られていた時も、先生方のアドバイスや手厳しい過去問の添削が心強い手助けとなりました。このような先生と生徒の結びつきが強い環境で勉強できたことを、今では幸せに思っています
A.T.(東京都私立頌栄女子学院高校):法学部私は高2の夏期講習会からトフルに入りました。トフルに入ってまず驚いたのは、スタッフの人たちが生徒一人一人の名前を覚えていたことです。また受験に関してのカウンセリングでは志望校や併願校の選び方などに関して、アドバイスしてくれました。
トフルの授業では先生が親しみやすく、普段習っていない先生でも気軽に質問することができました。受験期には入試問題んほ添削等もしていただきとても助かりました。
トフルは英語というイメージですが、先輩が世界史を受講していたこともあり選択しました。先生はすべてを知り尽くしたような方で、メリハリのある授業で入試に直結していたのでどこを覚えればよいのかがわかり入試ではとても役立ちました。はじめは自分がいかに世界史を覚えていなかったかが思い知らされましたが、受験前までにはほとんど覚えることができました。
またトフルでは素敵な友達もたくさんできました。一人で勉強していると集中できないこともありますが、一緒に頑張る友達がいると思うと頑張れました。受験生だから勉強しなきゃっていう気持ちばかりが大きくなり、あせることもありますが、自分は絶対合格すると信じて、精神的に強くなることが一番大切だと思います。
Y.S.(東京都私立跡見学園高校):法学部トフルが英語に特化した塾だと聞き、高2の春に入塾しました。はじめ国際系を目指していたので、英語にはそれなりに自信もあったのですが、難問ばかりというよりは、基礎から底上げをするようなトフルの授業はいつも新鮮で、得意科目というだけでとりわけ好きでもなかった英語の面白さを知ることができたと思います。
トフルの英語には趣旨が難解な長文も多く、それに慣れていたせいか、受験本番でどんな問題が出ても驚かなくなりました。私は英語以外の教科も全てトフルで対策していましたが、小論文などの細かいゼミが多いのでとても助かりました。
11月に入って進路を法学部に変更したときも、私に合ったサポートをしていただいて、感謝しています。少人数の強みを改めて実感しました。トフルに入って本当に良かったです。
R.S.(東京都立晴海総合高校):環境情報学部英語を読んで理解できるように勉強していました。受験英語に強くなることではなく、普通の英語ができるようになることを目標にしていました。受験前になっても焦らず、自分のペースを乱さないでいられたのが良かったのかと思います。
Y.M.(東京都私立跡見学園高校):文学部夏期講習などで予備校を渡り歩いた結果、トフルしかないなと強く感じた理由は、何よりも授業とテキストの質の良さでした。
特に英語は、レベルが高く内容が濃いのでやりがいの大きさと勉強の楽しさが他とは全く違いました。また少人数制なので常にあてられる緊張感と逆にいつでも質問できるという安心感がありました。
そして先生方やスタッフの方々の温かい姿勢は最後まで心の支えになっていたと思います。
C.H.(東京都私立豊島岡女子高校):総合政策学部私の受験生活を振り返ってみると、トフルゼミナールに非常に助けていただいたように思います。トフルでは、英語との接し方をたくさん教わりました。今では、トフルに通う前の私はどうやって英文を読んでいたのだろう?と思うほどです。しばらくすると英語力アップも実感できるようになりました。
選択科目では小論文の授業を取っていました。SFC志望だったため、少々厄介な小論文に慣れておく必要がありましたが、先生が丁寧に一人一人を添削してくださったので、楽しんで小論文を書けるようになりました。
特に高度な英語力が求められている大学を志望している人も多いと思います。私の場合はトフルで面倒を見てもらうだけで十分対応できました。通常授業で扱っている英文は難しいものが多いだけに、自然にかなりの読解力がつきます。(もちろん予習・復習は不可欠です。)
気軽に先生やチューターに質問できるアットホームな雰囲気が魅力的でした。
E.S.(東京都私立鴎友学園高校):経済学部受験を終えた今、自由な身の自分がいて、この一年間どれほどのものを我慢してきたかを実感しています。でも長いようで短かった一年間は何にも変え難い大切な思い出となりました。それは決して一言では言い表せない奥深い経験でした。楽しくもあり苦しくもあったためか、”寝る・食べる・しゃべる”というほんの些細なことに大いなる幸福感を感じています。
受験期は自分は必ず合格するという確信と現実にはサボっている自分とのギャップにあせりを感じ、計画が空回りしたこともありました。そして時には雑念を振り払うよう勉強しました。長い一年間、勉強がままならない時期があってもいいと思います。いかに要領よくマイペースに勉強を続けられるかが大事です。
私は本番で自身をもちつつ試験に望むことができました。それはみなトフルのおかげです。一年間お世話になったトフルの先生方、スタッフの方々、友達に心から感謝したいと思います。
Y.N.(東京都私立白百合学園高校):文学部私が大学に現役合格できたのも、このトフルで英語の力を伸ばせたからだと思います。受験で勝つためには、やはり英語の力が不可欠だと思います。ここでは、その英語力を身につけるための環境が非常によく整っていて、たとえば講師の先生方、スタッフの皆さん、チューターの方も皆親切でとても身近jな存在に感じることができました。特に志望校を決定してからの、先生をはじめとしたカウンセリングはとても有効だと思います。
そして何よりもこのトフルのアットホームな雰囲気に助けられたと思います。トフルゼミナールで勉強していれば強力な武器になります。教材の質もとても高いので、実際の試験の方が易しく感じられるくらいでした。トフルゼミナールにはとても感謝しています。講師の方々をはじめ本当にお世話になりました。ありがとうございました。
A.A.(東京都私立雙葉高校):法学部受験勉強期間を振り返ってみると意外とあっという間に終わってしまいました。トフルゼミナールに通い始めたのは高校3年の4月でしたが、少人数のクラスであったのですぐに友達もでき、受験に関する話をしたり、それ以外にも色々な話をすることができたので「勉強、勉強」というよりもリラックスした気持ちで受験期間を過ごしました。
受験勉強は4月にはやる気もあり、とにかくがむしゃらにやっていました。けれど夏休みが近づくとそのペースも徐々に落ちてきてしまいました。やらなさ過ぎはいけないけれど、やりすぎもよくないという風に思いました。大まかな目標を決めて勉強をするほうが良いと思います。
あと精神的な支えになるのは得意科目があることでした。私は英語が得意だったので、試験当日もこの科目だけは誰にも負けないという思いもあったし、試験が終わって英語が難しくできなかったとしても「自分ができないなら他の人もできていないはずだ」という気持ちになれたので、次の試験の科目にも影響せずに受けることができました。
受験する大学はあまり多くないほうが良いと思います。第一志望の大学が始めの方にあれば良いのですが、最後の方にあると疲労や集中力の限界もあるので大変だと思います。数受ければ受かるわけでもないので、自分の体力などに合わせて決めた方が良いと思います。
とにかく模試の判定がE判でも合格する確率はあるので、途中で志望校を変えたりせず頑張って勉強するのが大切です。努力は絶対に裏切らないと思います。
M.O.(東京都私立吉祥女子高校):文学部私は英語がとても苦手でどうにかしなくちゃと思い、トフルの春期講習会を受けました。授業が分かりやすく、フレンドリーで、しかも少人数なところに惚れ入学しました。トフルで使われている教材は難しかったですが、その分予習もしっかりするようになるし、先生の説明もしっかり聞いていました。段々模試などでも点数が取れるようになり、英文を読むのが楽しくなりました。
またトフルは英語だけでなく、他の教科もすごく充実していて、後期からは世界史の授業も受講しました。もともと得意だったのですが、分かりやすい説明のおかげで自分一人の勉強や学校の授業ではカバーできなかった部分が見えて効率的に勉強できました。他にもトフルの小テストや定期模試などを受けることができ、勉強する習慣がついたと思います。
私は家だとつい怠けてしまったので、トフルの空き教室などで友人と勉強できたことは、本当に助かりました。トフルなしでは合格はなかったと思います。ありがとうございました。
M.A.(埼玉県私立西武学園文理高校):文学部毎日習い事で忙しかった上に、学校の勉強も忙しかった私は、大学受験の勉強をどのように進めて行けばよいのか分からずに悩んでいました。そんなとき、トフルに入学しました。スタッフの方が親切に進路の説明をしていただきました。トフルのアットホームな雰囲気に、とても安心することができました。推薦パッケージコースでは、忙しかった私でも、きちんと推薦へ向けて準備、対策することができました。
何度も何度もエッセイや小論文を添削してくださったり、楽しく英語を教えてくださった先生方、優しく、家族のように温かいスタッフの方々、大学のことをたくさん教えてくださったチューターさん。私を支えてくださった皆さんに感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございました。
N.I.(東京都私立成蹊高校):法学部私の一年目の受験の失敗の原因は、自己分析不足にありました。自分の弱点がわかっておらず、必要な勉強ができていませんでした。また自分の実力もわかっていなかったため、どこかで受かるだろうという甘い気持ちで受験に望んだため全滅に終わりました。
本当に実力をつけなければとう強い気持ちに押されトフルゼミナールでの受験勉強を始めました。トフルでは自己分析を怖がらずに続けることを常に心がけ、またトフルの先生方にもたくさんのアドバイスをいただきました。そのおかげで成績もかなり伸ばすことができました。
それでも成績が滞ったり、精神的にもつらくなったときもありましたが、トフルの友達をはじめ、先生方、事務の方々の励ましやアドバイスに本当に助けられました。この一年やってこれたのはトフルのすべての人のおかげです。すごく感謝しています。
S.M.(東京都私立日本大学第二高校):環境情報学部浪人が決まってから予備校を決める際に、一年間マイペースにやりたかったので小規模で質の高い問題に取り組めるトフルにしました。
先生方も親身になって相談に乗ってくださるので、不安もあまり感じることがなく、受験することができました。
今、受験を終えて思うことは、毎日コツコツやってたことが意外と実力となって返って来たということです。やっている時は、くだらないような、意味のないことをやっている気はするけれど、ちょっとしたことが大事だと思います。
K.T.(千葉県私立市川高校):環境情報学部私が第一志望と考えていたSFCの入試は、英語に重点があります。英語の実力をあげなければなりません。
基礎的な英語よりも慶應大学に受かる英語を身につけたいと考えていた私には、浪人が決まってトフルゼミナールに入学しましたが、レベルの高い授業は大変意味のあるものでした。また、テキストに取り上げられている英文も興味深いテーマのものが多かったため、ただ、『英語を読む』のではなく、『英語で理解する』といった実践的なことを知らずうちに行うようになりました。
受験勉強で大切なのは、機械的に問題を処理していく感覚をもつことと、第一志望への熱意だと思います。しかし、熱意が先行しすぎると自分の実力を把握することを怠るようになりがちです。そんな時は、常に生徒の状況を把握してくれている先生やスタッフの存在が必要でした。受験に必要な熱意を長所として持ち続けられたことが勝因だと私は考えます。
Y.K.(愛知県立千種高校):総合政策学部浪人を決めてから予備校選びで、私がトフルを選んだ最大の理由は、アットホームであることで、質問のできる授業とともに大きな魅力でした。1年間、生活の中心になるトフルで、厳しい学習の疲れや不安を取り除くフォローを得られることは大きなメリットです。
質の高い授業、実力を磨くために行われる週1回のテスト演習、先生とのコミュニケーションを大切にしました。テスト演習は、自分の伸び・順位・目標のペースメーカーになるなどメリットは大きいのです。模試の結果をみながらの先生からのアドバイスはとても効果的でした。
長く深いスランプに陥った時に、カウンセリングで親身に問題解決を助けてくださり、自分のペースに戻る事もできました。浪人であとがなかった私にとって、今、振り返ってみてもとても嬉しいことでした。
アットホームとは、単純に仲が良い事ではないのです。努力を継続していける環境と合格する為に不可欠なサポートがトフルのアットホームなのです。
M.A.(東京都私立成城高校):商学部僕が受験を決意したのは高3の試験日の4ヶ月前でした。その頃は受験というものを安易に考えていました。トフルの入塾テストでは16点しか取れず、多くの予備校で合格するのは難しいと言われていました。それでも僕は毎日のようにトフルの個人授業や通常授業を受け、朝から晩まで勉強に励みました。しかし、高3時は第一志望校に落ちてしまいました。
やはり受験はそんなに安易なことではないんだということを改めて実感させられました。それからは、基礎をしっかりと固めようと思いトフルの標準クラスから始めることにしました。僕は先生にたくさんの質問をしましたが、先生はその1つ1つを丁寧に分かりやすく、僕が理解できるまでとことん教えてくれました。そのおかげで、一回目の模試では良い成績をとることができました。
しかし、その後の模試ではいい結果がでず、不安な日々が続きました。けれど、その時チューターや先生方が僕の話を親身になって聞いてくれて、たくさんのアドバイスをしてくれたことが僕にとって大きな支えになりました。だから、僕は試験まで頑張ることができたんだと思います。
そして、今年は第一志望校に合格し、4月から大学生になれることが決まりました。僕は受験勉強を通じて、様々なことを学ぶことができました。
今でもトフルの方々にはとても感謝しています。受験勉強はとても辛いことだけど、頑張ればその分必ず良い結果がついてきます。これからの受験生のみなさんも辛い時期が来ると思いますが、諦めずに頑張って下さい。
Y.M.(東京都私立三田高校):文学部トップ校の入試英語に太刀打ちできる英語の力をつけるにはどうしたらよいかと悩んでいたところ、出会ったのがトフルゼミナールでした。
英語は得意な方だったのですが、当時は構文を正確に取ることや、文章を深く読み込むといったことができませんでした。しかし、トフルのテキストのレベルの高さや、先生方の細やかな指導、経験豊かなスタッフの方々のサポートによって、英語の力を確実に高めていくことができました。
長い文章を読むことにも慣れ、文章を読む国語の力も同時に鍛えることができたため、入試本番では自信をもって解答することができました。
D.K.(東京都国立東京大学教育学部附属中等教育学校):文学部トフルの長文のテキストは難易度が高く、質も良いため、これをやるだけでも相当な力をつけることができました。授業も小人数だったため集中力がとぎれることがなかったし、アットホームな感じで楽しかったです。1年間お世話になりました!
M.K.(神奈川県私立公文国際高校):法学部私がトフルゼミナールに通い始めたのは高1の夏でした。毎日、部活ばかりで全然勉強をしない私を見て母が勧めたためです。正直なところ最初は行きたくはありませんでした。なぜなら自分ではそんなに英語が不得意だと思ってなかったからです。しかし実際に授業を受けてみて自分の英語力のなさを痛感しました。トフルゼミナールに通う前まではなんとか自分の知っている単語をつなげて意味を汲み取っていただけでしっかりと理解はしていなかったのです。そしてこのままでは自分の志望している大学に行けないかもしれないと思いあせりました。
結局、高3の5月頃まで毎日部活ばかりという生活は続きましたが、週2回は部活後にトフルゼミナールに来て、集中して授業を受け、着実に力をつけたことが、部活を引退してからの受験勉強の大きな助けとなったと思います。
冬になっても成績が伸びず、辛い時もありましたが、トフルゼミナールの先生方は本当に優しく、いつも励ましてくださり、なんとか合格を手にすることができました。最後は合格したいという気持ちが大事だと思います。合格の秘訣は特にありません。頑張ればその分結果がついてくるというのは本当だと思います。
トフルゼミナールでお世話になった先生方やスタッフの方には本当に感謝しています。ありがとうございました。
CLOSE

校名を記した門標のないことが象徴的に現しているように、学ぶ意欲のある人に可能な限り学問の場を提供できるように、他大学に先駆けてさまざまなカリキュラムやサービスなども取り入れています。また、コンピューター導入が進んでおり、インターネット上でも研究室の発表やサークル活動のお知らせなど、さまざまな情報を発信しています。
語学や情報処理科目の充実、豊富なカリキュラムと自由な発想でより良い教育環境を実現しています。
また、商学部ではインターンシップ制度を導入し、企業のほか、官公庁や地方自治体、NGOなどへの派遣など、外の世界への太いパイプを持っています。
また、社会に出て大学で学んだ分野とは別の仕事に就くというのはよくあることですが、その際にも学んだことをバネにし充分に活躍できる幅広い実践力を養えるような授業を展開しています。
「社中協力」という伝統のもとに、卒業生との強い結びつきが今も連綿と生きています。これは慶應大学独自の呼称で、在学生、卒業生、教職員すべてを「社中」と呼んでいますが、この協力体制が、さまざまな企業・団体・地方自治体からの奨学金制度、また多方面に進出した先輩たちとのコラボレーションを通じての就職活動など、さまざまなネットワークとなって広がっています。この「社中」の交流は「独立自尊」(独立とは「国家権力や社会風潮に迎合しない態度」、自尊とは「他人を思いやる気持ちを持ち自己の尊厳を守り、何事も自分の判断・責任のもとに行うこと」)の精神と並んで慶應大学の特徴となっています。
創設者である福沢諭吉が慶應義塾の目的を簡明に表したものとして、以下の一文が知られています。
「慶應義塾は単に一所の学塾として自から甘んずるを得ず。其目的は我日本国中に於ける気品の泉源、智徳の模範たらんことを期し、之を実際にしては居家、処世、立国の本旨を明にして、之を口に言ふのみにあらず、躬行実践、以て全社会の先導者たらんことを欲するものなり」
この目的を理解した上で、各学部の定めるアドミッション・ポリシーを確認することが重要です。 (慶應大学ホームページより)
多様な領域をカバーする10学部が、自由な発想に立って個性と特色ある研究活動を進めています。
*最新の入試情報や出願条件などは必ずご自身にて慶應大のWebサイトでご確認ください。
全学部で行われており、3教科での受験が基本ですが、総合政策学部と環境情報学部は2教科での受験も可能です。
また、2027年度以降の入試においては、経済学部において以下の通り2教科での受験に変更されます。
A方式:英語200点 + 数学200点
B方式:英語200点 + 地理歴史(世界史、日本史いずれか)200点
2025年度入試より文学部で導入されました。内容は以下の通りです。
英語 150点 独自試験または外部試験利用の選択
*外部試験利用の基準は英検CSEスコア2500以上(受験級および合否結果は問わない)
地理歴史(世界史、日本史いずれか) 100点
小論文 100点
法学部のFIT入試、文学部の自主応募制推薦、SFCおよび理工学部のAO入試があります。
各学部で帰国生入試、外国人留学生入試が実施されています。 また、経済学部では英語による学位取得のプログラム(PEARL)があります。 *帰国生入試については当校の帰国生専用ページをご参照ください。 https://tofl.jp/kikoku/index.php
慶應大学法学部のFIT入試は、出願書類「志望理由書」「自己推薦書」の提出、さらに模擬講義後に論述形式の試験があり、最後にグループディスカッションと個別プレゼンテーションで合否が決まります。
トフルゼミナールの慶應法学部FIT入試対策クラスでは、完全プロ講師による少人数・ゼミ形式の専門授業で出願書類の作成から2次試験の論文試験対策・グループディスカッション・面接対策まで徹底的にサポートしていきます。
この入試では「志願者調書」「自己推薦書」「志望理由書」の3種類の書類を作成し提出しなければなりません。この3つの内容が少しずつ重なって関連しながら、全体としてあなたの意欲や人間性を表すように話題を割り振りながら作っていきます。
「志願者調書」は年度によって多少変更される場合もありますが、4つほどの質問に答えることで、これまでのあなたの「足跡」を示します。各項目は300~400字と短いので、ポイントを絞って簡潔に表現する必要があります。
「自己推薦書」は用紙が白紙の自由記述形式で、文字だけではなくイラストを描いたり、写真を貼ったりすることができます。ですから、ここではできるだけ個性的に、これまでの活動実績をアピールしてください。
最後に「志望理由書」は、志望理由、入学後の学習計画、将来の夢を2,000字以内で書くもので、書類の中で最も重要です。慶應大学法学部は「次世代のリーダーを養成する」ことをモットーにしていますから、将来について高い目標を掲げ、あなたがそれを実現させる重要なステップとして、この法学部で学ぶ必要がある、と強く訴えられる中身を作っていきましょう。
FIT入試のキーワードは「総合力」です。講義理解力試験での情報整理力と文章作成能力、集団討論試験での要点把握力と立論能力、プレゼンテーション試験での表現力、そして提出書類での活動実績と問題意識。合格のためには、それらをバランスよく発揮することが必要です。多くの大学が実施しているAO・推薦入試の中でも最難関の一つと言えるでしょう。
その対策のためには、まず自分の弱点を知ることが重要です。文章作成能力や立論能力が弱点だと感じたら、小論文の勉強をすることが有効です。活動実績が弱いと感じたら、もう一度自分の中学・高校生活を見つめ直しましょう。結果としては大きな実績でなくとも、取り組みの過程であなたの特長が発揮された出来事がきっとあります。
本番でも、どれか一つの試験で突出した能力を示そうとするのではなく、それぞれの試験は一つの要素に過ぎないと考えて冷静に対処することが合格につながります。
ときどき出願まで提出書類の作成ばかりに一所懸命になって、二次試験対策を怠る人がいますが総じて良い結果にはなっていません。はじめからFIT入試全体を見据えて、能力の向上に努めましょう。
慶應大学SFCのAO入試は、出願書類「志望理由・自己アピール・学習計画書」の提出による一次審査と、これに約30分の個別プレゼンテーションおよび面接で合否が決まります。
トフルゼミナール慶應SFC AO入試専門クラスでは、SFCの教育理念や研究の特徴の解説から始め、1次選考の書類作成、2次選考の個別プレゼンテーション・面接対策まで丁寧に指導します。
クラスでは互いの志望理由を発表し、プレゼンテーションの練習を行うとともにSFCに必要な発想力を養います。慶應SFCのAO入試を熟知し、多数の合格者を指導してきた専門プロ講師による丁寧な添削指導で説得力ある書類を仕上げます。
慶應大学SFCのAO入試は、出願書類「志望理由・自己アピール・学習計画書」の提出による一次審査と、これに約30分の個別プレゼンテーションおよび面接で合否が決まります。
トフルゼミナール慶應SFC AO入試専門クラスでは、SFCの教育理念や研究の特徴の解説から始め、1次選考の書類作成、2次選考の個別プレゼンテーション・面接対策まで丁寧に指導します。
クラスでは互いの志望理由を発表し、プレゼンテーションの練習を行うとともにSFCに必要な発想力を養います。慶應SFCのAO入試を熟知し、多数の合格者を指導してきた専門プロ講師による丁寧な添削指導で説得力ある書類を仕上げます。
SFCのAO入試のキーワードは「積極性」です。SFCは好奇心が強く、行動力のある学生を求めています。例え弱点があっても、一点突破の得意分野があればアピールすることができます。
ただし「得意」に裏付けがなく、ただ関心が強いというだけではダメ。問題意識を持った分野について、これまでに何らかの取り組みを行っていて、それをさらに進めてようとしている、という実績を提示する必要があります。
このAO入試では、一次試験で書類審査が行われ、二次試験で面接(プレゼンテーションを含む)が行われますが、どちらでも上記の「問題意識」と「実績」を具体的に示すことが求められます。問題意識を深め、それをどう表現するか─それが対策のポイントとなります。
慶應大学文学部自主応募は、総合考査と呼ばれている小論文形式のテストにより、各種資料に対する理解力、文章表現力や和文英訳の力などが試され合否が決まります。
トフルゼミナールの慶應文学部自主応募入試準備クラスでは、圧倒的な練習量と添削指導量で論述力、読解力、和文英訳力を身につけていきます。
文学部自主応募入試のキーワードは、「読書量」です。この入試は「推薦」と言いながら簡単な自己推薦文を提出する以外は、面接試験もなく、ほぼ出願条件のクリアと筆記試験だけで合否が決まります。
筆記試験には2種類の小論文問題があり、一方は課題文型、他方はテーマ型です。さらにその課題文の一部を英訳する問題が2問あります。
この小論文試験で「ものを言う」のが読書経験の厚みです。そこはやはり「文学部」の試験であり、人文科学分野の素養が試されているのです。
まず、小論文試験の一方である課題文型問題では、思想・芸術論・文学論など、高度に抽象的な内容の文章が出題されています。 こういった種類の文章に慣れていること、あるいはそういった文章が題材にしている文学や芸術作品に親しんでいることが、答案のレベルに影響してきます。
要約の設問をそつなくこなすことができても、自分の考えを書く設問では、人文科学分野への関心の程度が答案に表れてしまうのです。
和文英訳問題でも、まず抽象的な内容の日本語文をわかりやすい日本語表現に「翻訳」することが必要で、英語力以前に一定の読解力が要求されます。
また、もうひとつのテーマ型小論文ではまさに文章センスが問われており、どれだけ「名文」を読んでいるかが答案作成のカギになります。
全国17校舎で入試説明会を開催しています。オンラインでも参加可能です。 個別相談も受け付けています。