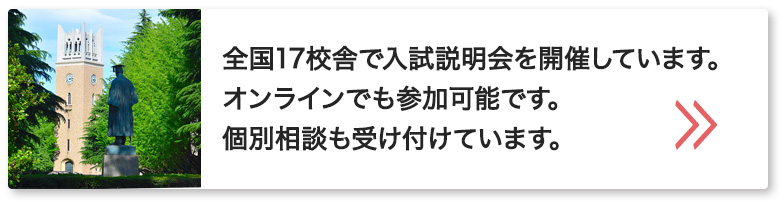早稲田大学は近年創立140周年を迎えた伝統を誇り、数多くの卒業生たちが様々な分野で活躍する、まさに日本の「私学の雄」と言えます。かつては質実剛健の学生気質から「蛮カラ」のイメージがありましたが、実は早稲田の最大の特徴はあらゆる人材を飲み込んで、その多様性をエネルギーにする「人材の坩堝」である点です。
今や全世界から学生が集まってくる国際的な大学への飛躍を目指し、国際教養学部以外にも英語で授業を行う学部も複数あります。
入試には一般選抜、総合型・学校推薦型選抜があります。
このページでは、早稲田大学の合格に必要なことから、早稲田大学の教育の特徴まで説明します。

最難関私立大学の一つと言われる早稲田は、入試改革に最も積極的に取り組んだ大学でもあります。
共通テスト受験を必須とし、学部独自問題を大きく変えた政治経済学部と国際教養学部(2025年度からは社会科学部も)、英語4技能資格試験を導入した各学部と、様々な変化が生じています。
学部独自問題では、政治経済学部の総合問題は日本語と英語の長文問題に加え、表やデータグラフも出題される難度の高いものです。
2025年度から変更となる社会科学部でも、総合問題において図表やグラフの読み取りに加えて記述問題が出題されます。国際教養学部は英語のみであるものの、その難度は私大最難関と言えるレベルです。
いずれの学部であれ、早稲田大学の入試は全ての科目で全般的に長文の量や設問の数が多い点で難易度が高いものです。特に文系においては英語の配点が高くなり、合否を左右する科目となり対策の優先度は高いと言えます。
年度や学科により大きく異なりますが、過去2年の一般選抜の倍率は以下の通りとなっています。
| 2024年度 | 2025年度 | ||||||
| 学部 | 入試方式 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 文 | 一般 | 7,330 | 934 | 7.8 | 7,954 | 679 | 11.7 |
| 英語4技能利用 | 2,307 | 326 | 7.1 | 3,145 | 383 | 8.2 | |
| 共通テスト利用 | 873 | 191 | 4.6 | 1,039 | 194 | 5.4 | |
| 文化構想 | 一般 | 6,618 | 783 | 8.5 | 6,991 | 665 | 10.5 |
| 英語4技能利用 | 2,355 | 339 | 6.9 | 3,139 | 448 | 7.0 | |
| 共通テスト利用 | 993 | 206 | 4.8 | 1,142 | 233 | 4.9 | |
| 国際教養 | 一般 | 1,229 | 380 | 3.2 | 1,303 | 362 | 3.6 |
| 政治経済 | 一般 | 2,168 | 760 | 2.9 | 2,613 | 654 | 4.0 |
| 共通テスト利用 | 5,042 | 1,602 | 3.1 | 3,964 | 780 | 5.1 | |
| 法 | 一般 | 3,809 | 829 | 4.6 | 4,110 | 726 | 5.7 |
| 共通テスト利用 | 2,044 | 567 | 3.6 | 2,750 | 553 | 5.0 | |
| 商 | 一般:地歴・公民型 | 7,039 | 755 | 9.3 | 7,767 | 754 | 10.3 |
| 一般:数学型 | 2,329 | 400 | 5.8 | 2,693 | 394 | 6.8 | |
| 社会科学 | 一般:総合問題型 | 7,833 | 921 | 8.5 | 3,934 | 692 | 5.7 |
| 一般:数学型 | 1,821 | 310 | 5.9 | ||||
| 共通テスト利用 | 1,384 | 361 | 3.8 | 2,120 | 424 | 5.0 | |
| 教育 | 一般 | 11,401 | 2,142 | 5.3 | 12,204 | 2,111 | 5.8 |
| 基幹理工 | 一般 | 4,090 | 1,097 | 3.7 | 3,978 | 1,029 | 3.9 |
| 創造理工 | 一般 | 2,950 | 753 | 3.9 | 3,017 | 744 | 4.1 |
| 先進理工 | 一般 | 3,798 | 1,075 | 3.5 | 3,958 | 979 | 4.0 |
| 人間科学 | 一般:国英型 | 5,926 | 1,339 | 4.4 | 2,802 | 473 | 5.9 |
| 一般:数英型 | 759 | 229 | 3.3 | ||||
| 一般:数学選抜方式 | 633 | 203 | 3.1 | ||||
| 共通テスト利用 | 1,075 | 278 | 3.9 | ||||
| スポーツ科学 | 一般 | 1,909 | 566 | 3.4 | 1,313 | 253 | 5.2 |
| 共通テスト利用 | 1,131 | 274 | 4.1 | ||||

多くの学部において、英語の配点比率が高く、最も合否を左右する科目です。 入試問題の全般的特徴としては「オーソドックスな良問がそろっている」と言えます。ただし、オーソドックスな良問ということは、問題文のある程度細かな点から、全体の要旨(メインアイディア)まで正確に把握しているかをしっかり試されるということです。小手先のテクニックやフィーリングではなく、⾧期的にこつこつと訓練を積んだ者が確実に得点できる問題になっているのです。
◆どの学部においても英語の配点が高い!
政治経済学部:38%、法学部:40%、教育学部:33%、商学部:40%、社会科学部:42%、国際教養学部:50%、文化構想学部:38%、文学部:38%、人間科学部:33%、スポーツ科学部:41%、 理工学部:33%
※ 政治経済学部は独自試験の配点を英語50%として換算した場合。
英語4技能を利用した入試を実施している学部では、受験チャンスの拡大や合格可能性の向上につなげるためにも、取得は必須です。併願大学の対策にもつながるため、早期の準備が有効です。
◆英語4技能資格試験利用入試を実施している学部
文学部・文化構想学部…出願基準:TOEFL60・IELTS5.5・英検2200以上
※2025年度より募集人員増!…文学部:50名→85名、文化構想学部:70名→110名
国際教養学部… 20 点加点:TOEF L95 ・IELTS7.0・英検1級以上、14 点加点:TOEFL72・IELTS5.5・英検準1級以上、7点加点:TOEFL42・IELTS4.0・英検2級以上
受験のためだけではなく、将来のためにより幅広く英語への興味を持続できるかどうかが重要であり、勉強の過程でさらに英語が好きになるのが理想です。

早稲田大の合格に向け、高3・高卒生向けの実戦的な対策と、高2・高1生向けの早期準備のための対策があります。
トフルゼミナールは、それぞれに合わせた対策講座を提供しています。
受験生向けの授業は基礎力・総合力を伸ばすためのものから、早稲田大専用対策の講座まで幅広いラインナップを揃えています。英語以外にも、国語、歴史、数学、情報の対策講座があります。
部活で忙しい方や近くに校舎がない方も安心してください!
授業は通学型 / オンデマンドから選ぶことができます。
以下は、対策講座の例です。
この講座ではどんな場面にも通用するランゲージ・スキルとしての読解力、それを支えるヒューマン・スキル(思考と知識)を鍛えます。多様な性格を持つ英文のそれぞれの読み方に習熟できるように、パッセージは以下の3つのタイプに分かれています。
Type 1=Academic:教科書・TOEFL Test・百科事典に典型的に見られるPassageの読解を目指す。
Type 2=Critical:学術的な評論・国内難関大学の長文に典型的に見られるPassageの読解を目指す。
Type 3=Descriptive/Diverse:描写的・表現的な性格を有するPassage(物語・ジャーナリズムなど)の読解を目指す。
また、それぞれの英文のタイプに適合したnotes(注解)、qusetions、review(復習)のパートがあり、reviewにはReadingとListeningの両方の強化に繋がる要素が含まれています。
さらに、すべての英語力の基礎となる語彙力を高めるためのVocabulary、また英文の文化的背景に目を向けさせるためのExpanding your Horizonsというコラムが各レッスンにあります。
英語の4技能(読む・書く・聴く・話す)すべての基盤となる文法・語法力と、それに基づく「書く」技能を養成することを目標とした科目です。Lev.3までの知識の習得を前提として、Lev.4では大学受験やTOEFL Testなどの英語資格の試験対策につながる実戦的な問題演習を多く取り入れます。
Grammarのパートは、各レッスンに一定の文法的テーマと項目を設け、年間を通して英文法の全体が網羅されます。Writingのパートでは、各レッスンの文法項目の理解に基づくsentenceレベルの英作のほか、大学受験やTOEFL Testで重要となるエッセイライティング(意見・自由英作文)の導入的演習を行います。
正しい音声の習得を徹底し、より実践的なリスニング力およびその助けともなるスピーキング力の育成を目指します。
Lev.3/Lev.4では、これまでのLev.1/Lev.2と違って、スピーキングよりリスニングの比重が高くなります。具体的には、大学受験のリスニング、英語資格試験のリスニング・スピーキング学習に移行するために必要不可欠な能力を育成します。
大学受験においてもリスニングの重要性は高まっており、英検、ELTiS、TEAP、TOEFL/TOEIC L&R Test、IELTSなど各種資格試験の重要性も増しています。いずれの対策を行うにしても、この講座がその準備の土台となります。
英検、TEAP、TOEFL、IELTSなど英語資格試験の対策講座があります。現在の英語力や志望校、方式に合わせて選ぶことができます。
グローバル社会におけるキーワードについて、歴史的背景や関連する事柄を学ぶことで社会的な視野を育成します。さまざまなテーマごとに、①歴史を振り返り、②現在を確認して、③2050年がどうなっているかを構想します。論文やエッセイ対策にも有効です。
アカデミックな文章の読解、図表データの読み取り、根拠を持った主張構築などの練習を通して、そうした日本語の「コア(核)」となる技能を磨くとともに、何のために大学に進学するのかを考える機会を設け「現代文」「小論文」や、総合型・学校推薦型選抜の準備を行います。
「社会的な問題に対して知的好奇心を持って関心を持とうとする積極性」「そして自分から考え、自分の考えをまとめ、意見として述べる」「さらに自己をアピールできる表現力を持つ」ことを養成するための講座です。総合型・学校推薦型選抜での自己アピールや、ディスカッション形式の面接および小論文対策の基礎づくりに有効な講座です。
実際に出題された読解・文法・語法問題に取り組み、早稲田大・慶應大突破のために必要な英語力を体感し、合格に向けて一歩リードするための高2生向け講座です。
出題分野、傾向、形式別に構成されたテキストを使用し、問題分析を行い、早稲田大・慶應大で求められる英語力はどのようなものなのかを「しっかり知る」ための高2生向け講座です。
以下は、対策講座の例です。
⾧文読解力をつける3要素、「効率的かつ正確に内容を把握する技術を知る」「多くの⾧文に触れセンスを磨く」「的確な問題解法を身につける」を、総合的に高めることが目的です。フレーズ・センテンス・パラグラフ・パッセージという英文のそれぞれのレベルに合致した「読解のメソッド」を身につけ、正確で効率的な⾧文読解のための技術を体系的に習得します。
春学期では、英文法項目を体系的にまとめた問題形式のテキストで、英文法の全体像がみえるように解説します。基本的文法項目の理解に加え、弱点や誤りやすい事項に関しての完全な整理を行います。 秋学期では、早慶上智を含めた難関大学対策用の問題演習により、幅広い応用力を養成するとともに、いかなる形式の問題や難問にも対応できるよう指導します。
英検、TEAP、TOEFL、IELTSなど英語資格試験の対策講座があります。現在の英語力や志望校、方式に合わせて選ぶことができます。
正しい音声の習得を徹底し、より実践的なリスニング力およびその助けともなるスピーキング力の育成を目指します。大学受験のリスニング、TOEFL Testのリスニング・スピーキング学習に移行するために必要不可欠な英語能力を育成します。
総合型・学校推薦型選抜対策の基本講座です。主に自己推薦書・志望理由書などの書類作成や面接準備を行います。
入試でキーになる要素は、自己を社会の中に位置づけて経験や将来像を明確なイメージにまとめる自己把握力と、そのイメージを伝えるためのコミュニケーション能力です。高2冬期からスタートし、文章作成練習を通して表現のスキルアップを図りながら志望動機を明確にしていきます。夏期から秋学期にかけてはその成果を提出書類にまとめあげます。
総合型・学校推薦型選抜の筆記試験に対応した小論文講座です。前半では句読点や原稿マスの使い方などの書き方の基礎をはじめ、どのように「考える」か、ということを主眼に学習を進め、担当講師による徹底的な添削で少人数制ゼミならではのきめ細かい指導をしていきます。小論文の基本から説明してレベルアップを図り、後半は実践的な問題練習を行うとともに、大学学部系統別に必要となる知識インプットの方法をアドバイスします。
ハイレベルな社会科学系小論文のために、社会問題に関する知識や背景の理解のインプット講座です。課題文を読んで理解度をチェックし、論述問題に挑戦します。
社会科学系学部の総合型・学校推薦型選抜のための早期対策。政治・法律・経済・社会などに関する課題文を読んで、グループ討論や小論文の作成を行います。
早稲田大などの難関私大や国公立大2次対策を視野に入れた上級読解力養成講座。論理的に読む技術になじむことから始めて、高度な文章読解力を習得し合格答案への導き方を習得していきます。本科では軸となる読解力・記述力の養成を図り、講習会で出題傾向に即した問題演習を行います。
古文最難関校対策の講座。春学期は単語・文法を踏まえて、難易度の高い文章で、なんとなくではなく、本文にきちんと対峙して深く読み込むことでゆるぎのない読解力の養成を目指します。秋学期は、ジャンルごとに異なる読解のアプローチを学びつつ、より実戦的にさまざまな設問に対応できるようにしていきます。
特に難関大学の正誤問題には正確な知識が必要となるため、正確な知識と自信が身につくように指導します。春学期は原始・古代から織豊政権まで、秋学期は江戸時代から現代までを扱い、直前期には、頻出のテーマ史を中心としたテストゼミが用意されおり効果的に即戦力をつけることができます。
春学期は、人類の誕生から始めて前近代までを終わらせ、秋学期にはルネッサンス以降から近現代を扱います。早慶上智やトップ国公立などの最難関校の入試問題に対応できるよう必要な知識の完全習得を目指します。直前期は、テストゼミ形式で総合力確認と文化史の復習を行います。
過去に出題された問題の演習を通して基本的な公式から学習していきます。共通テストの数学は、助詞や接続詞に着目することが大切で、重要なヒントになっていることが多いのです. 年度によっては解きにくい問題が出されることもありますが、多くの問題を解いていけば動揺しないようになります。
過去5年間ほどにわたり早稲田大学の各学部で出題された問題のうち、読解問題(総合問題・内容把握・空所補充・会話文)を中心に、文法・語法・作文を含め、重要ポイントを整理し解法を伝授します。
過去に実際に出題された問題から、徹底的にその出題傾向を分析し今後の学習指針を示します。合わせて英語4技能テストの提出に備えたTOEFL Testや英検対策をお勧めします。
授業では出願書類添削と論文審査および面接の対策をします。とくに論文審査(日本語)はレベルが高く、すべてが論述による解答方式で意見を述べる小論文も毎年含まれています。講座では、実際の論文審査問題をもとに解法へのアプローチを、添削指導を交えながら授業を行っていきます。
いち早く対策を始めた実績が合格結果へとつながり、これまでの指導ノウハウが凝縮された講座です。高度な英語力を養成するため100分×6回の授業時間を確保するほか、筆記試験対策を添削指導つきで徹底して行います。
一般入試では長文読解、自由英作文、英文を読み日本語で要約する問題の3種類が出題されます。この対策として、オリジナルの予想問題を使用し、ハイレベルな英語読解力、運用力を養成します。
文法・語法・語彙・発音・アクセントなどの諸知識から、全文内容把握に基づく読解問題、英作文構成力などバラエティーに富んだ出題が特徴で、どこが欠けても致命傷になります。講座では、過去問の分析から解法へのステップを指導して、予想問題演習も交えて合格へ導きます。
文法・語法の知識の差が、英語重視の難関大で合否を分けるケースが多々あります。この講座では、文法問題および細かい語法や類義語のニュアンスなどの整理を行い、入試レベルでは最高難度の文法をマスターします。
- 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
- 「早稲田の英語」「東京外大の英語」「慶應の英語」など執筆多数
早稲田大学は近年創立125周年を迎えた伝統を誇り、数多の卒業生たちが様々な分野で活躍する、まさに日本の「私学の雄」と言えます。かつては質実剛健の学生気質から「蛮カラ」のイメージがありましたが、実は早稲田の最大の特徴はあらゆる人材を飲み込んで、その多様性をエネルギーにする「人材の坩堝」である点でしょう。
私個人も、早稲田の杜に4年間学ぶ中での最大の収穫は、実に様々な個性とふれあい、多大な刺激を受け、考え、そして人間として成長できたことです。学究にせよ、ゼミ活動にせよ、そしてサークル活動にせよ、このような多様性の中でもまれるという貴重な経験は早稲田のような全国から学生が集まってくる総合大学でこそ可能になると思います。
その早稲田が「創立125周年」を機に、“第二の建学”を宣言しています。そのキャッチフレーズは「グローバルユニバーシティー」。「早稲田」から「WASEDA」へ、世界中でトップクラスとして評価される大学を目指すというものです。
具体的に大学が打ち出している「WASEDA」確立の柱の中には、「多文化が共存・融合する地球社会における知の基盤の構築」、「地球上の至るところを学びの場とし地球共同体のリーダーを育成」、「日本文化・アジア文化の国際的研究拠点を形成」などの目標が掲げられています。
このような大きな柱からは、これまでの早稲田の特徴であった「多様性の共存」を国内規模から世界規模へ広げていこうとする伝統の「継承」と「発展」がはっきりと読み取れます。先ほど、「全国から学生が集まってくる」と書きましたが、今や全世界から学生が集まってくる国際的な大学への飛躍を目指しているのでしょう。比較的新しい国際教養学部は、授業全てを英語で行い、1年間の海外留学が必須とされ、さらに学生の約4割を留学生が占めているといった点で、まさにその目標の象徴的な存在です。
このような早稲田の方向性を考えると、今後早稲田がどのような学生を求め、どのような能力を入試で推し測ろうとしているのかも見えてきます。まずは、様々な文化・考え方を理解し、それらの違い認めつつもそれを融和的に乗り越えていく柔軟性。それらを学び、吸収するための高い語学力(またはその潜在性)、自らの考えを端的に表現し伝えるコミュニケーション能力、そういった能力を社会で生かしていくための社会的関心や行動力‥‥などなど。簡潔に言えば「国際人となり得る資質」と言えるでしょう。そしてこのような資質を、受験生の英語力と日本語力を試すことによって推し測っていこうとするに違いありません。
早稲田を目指す受験生には、細かい知識の吸収に終始するのではなく(もちろん知識の吸収も大切ですが)、上に挙げたような資質を身に付けようとする根本姿勢を常に持って日々の学習に取り組んでいってもらいたいものです。その積み重ねが、きっとあなたを早稲田の杜に導いてくれるはずです。





トフルと言えばやっぱり英語でした。基礎力はある程度ついていたつもりでいましたが、トフルに入ってからそれまで出来ていなかったことがどんどんわかりました。
それを埋めていたらいつの間にか読むスピードも読み方もよくなっていたという感じです。「トフルと言えば英語」と言いましたが、国語、日本史の授業もすごく良かったです。
少人数のよさがとても感じられました。質問が気軽に出来たり添削してもらえたり…ほんとトフルには感謝感謝です。ありがとうございましたぁ~!!!!
夏休みは週5回TOEFLの勉強をして、週一回早稲田国際教養AO対策ゼミをとっていました。この中で、私が入試のとき特に助けられたのはライティングとリーディング、そしてAOゼミでした。大学に提出する書類に少しでも自信が持てるトフルのスコアを記入するには、TOEFLのどのパートも高得点が必要です。早稲田の問題は少しかわっていますが、筆記試験での問いに答えやすくなると思います!
指導して下さった先生方とスタッフの皆様、本当にお世話になりました!!特に安藤先生には出願の締め切りギリギリまでエッセーの添削をして頂いたり、面接の練習をしていただいて、ホントにありがとうございました。練習したのと全く同じことを本番でも聞かれました!!!
僕は高1年の頃に自分が苦手な英語を伸ばすために、また部活との両立ができるような塾を探していたときにトフルに出会いました。トフルは少人数で授業を行い、先生方も熱心に教えてくれたので、英語の成績は自分が思っていたよりも伸びました。
また、トフルはアットホームな雰囲気だったので、次第にトフルに行くのが好きになり必修曜日以外も毎日トフルに行くようになりました。そのため、大手予備校にありがちな授業に出ないといった悪い習慣はありませんでした。
さらに、僕は家で勉強できる性格ではなかったので、トフルに毎日来て勉強しました。トフルでの勉強は集中できて、効率的に勉強できました。
僕はトフルのおかげでつらいといわれている受験勉強もつらいと感じることなく、勉強できました。本当にトフルには感謝しています。
トフルゼミナールに入った高2の秋でした。それまでは大手予備校に通っていたのですが、生徒を指さずに先生が一方的に講義していたので、何となくボーッとしているだけで成果もあまり上がりませんでした。でも、トフルゼミナールは教室が小さく、先生も積極的に生徒に問いかけるので、予習もせずに「なんとなく」椅子に座っているだけでは授業について行けないのです。だから予習をして、授業の後は先生に質問し、帰ったら復習するというサイクルが自然と身につきました。
高3になって、さらに本格的な受験勉強を始めました。僕は私大文系型の受験をするつもりだったので、最も重要になる科目はやはり英語です。トフルゼミナールの英語の授業は、受験の知識やテクニックだけではなく、先生が英語の背景にある歴史や文化の話もしてくれて、楽しんでクラスに参加することができました。また、校内模試は問題が難しくて、そのぶんとてもやりがいがありました。入試の直前には、志望校別の「One Day模試」が開講され、先生が入試問題のエッセンスを解説してくれました。先生の激励の言葉は入試の心強い味方になりました。
大学受験は自分の努力次第。でも、それを最大限サポートしてくれるのがトフルゼミナールだと思っています。
僕がトフルに入ったのは高2年の夏休みアメリカ留学から帰ってきて大学受験の事を考えた時に英語を武器として伸ばしてくれる予備校に入るしかないと思った。そしてトフルに出会ったのである。
少人数制の授業なので身につきやすく、スタッフの方も気さくな人たちばっかりだったので、すぐに溶け込むことができた。他の予備校の模試を受けるとダントツに英語だけは良かった。三年になると、苦手な国語に力を入れ、英語に手が回らなくなることもあったが、二年の時の勉強内容のレベルが高かったせいで、英語のレベルは落ちなかった。
そして、センターの時期には殆ど受験体勢は万全になっていた。受験ではコケたところもあったけれど、志望大学に入ることができた。やはり、英語は強力な武器だったことを確認し、トフルに入ったことがよかったと思っている。合格できてよかった!!
- 他の体験談も見る
-
K・Y(東京都立南多摩高校):教育学部
トフルに入学してからしばらくの間は、授業についていくのに必死で、毎回ドキドキしながら出席していました。先生に手紙で、下のクラスに移りたいと相談したこともありました。その時、先生は私の言葉ひとつひとつに丁寧にコメントしてくださり、私は先生の励ましのおかげでそこで踏ん張ることが出来ました。
しばらくして慣れてくると、授業も一週間で一番楽しみな時間になり、成績も伸びて自信がつき、志望校のレベルも上げていきました。私は優柔不断なためなかなか受験校を決められず、毎週先生に相談に行った時期もありました。その時も、先生は親身になって一緒に考えてくださり、良いアドバイスをたくさんくださいました。
不安で辛い時期もあったけれど、トフルの先生やスタッフの方々に支えられ、励まされ乗り切ることが出来ました。トフルでの1年間と身につけた英語力は私の宝物です。トフルにはとにかく感謝!!今まで本当にありがとうございました。
E・S(東京都立立川高校):国際教養学部独学での受験勉強に限界を感じていた三年生の四月ごろ、僕はトフルゼミナールに出会いました。何も考えずにただ入る事を決心したのですが、授業が始まると、自分の判断は大正解だったと確信しました。
トフルの英語はとても難しかったけれど、やり応えがあり、知的好奇心をかき立てるものでした。すっかりトフルの英語にほれ込んだ僕は、学校の英語そっちのけで予習復習をしていたほどです。トフルの素晴らしいところは授業だけではありません。少人数制の塾だったので、先生やチューターは親身になって相談にのってくれ、また多くの友達もできて、受験勉強の励みとなりました。
M.O.(東京都立南多摩高校):文学部浪人して本当に良かったと思える今があるのは、この大切な一年間をトフルに委ね、精一杯頑張ることが出来たからです。
トフルは一般的な予備校というイメージを一掃します。講師は皆、生徒に対して親身になってくれて、勉強以外でもたくさん面倒を見てくれます。英語の授業で使うテキストは入試レベルを遥かに超えているので、実力ばかりか自信もかなりつきます。私は全ての入試で英語が得点源になりました。
英語のトフルと言われながらも国語や歴史の講師の質もとても高いです。現代文や日本史では個人的に論述の添削をしてもらったことが、とても力になりました。
また、少人数の授業では生徒同士の仲もすぐにも深まるので、一日の大半をトフルで過ごしていた私にとって、とても居心地の良い場所でした。いつも笑いの絶えない環境の中にいた私には、辛いはずの受験生活も「楽しかった!」の一言に尽きます。
Y.N.(東京都私立豊島岡女子高校):教育学部私は高校1年生の時に、できるだけ少人数のクラスで英語をしっかりできる塾に入りたいと思い、トフルゼミナールに入学しました。
トフルは授業も面白く、わかりやすいのはもちろんのこと、なんと言っても塾全体の雰囲気が格別でした。受付のスタッフの皆さんはいつも笑顔で、話しかけてきてくれ、いろんな相談にものってくださいます。
私は高3の夏休みが終わってもなかなか志望校を決定することができませんでした。けれど、スタッフの皆さんやチューターさんが親身にカウンセリングをしてくれたおかげで、目標を定めてそれに向かって突き進む事ができました。受験直前も、不安になったときや焦ったときなどに電話をいただくこともしばしばでした。電話のあとは不思議と不安がなくなって、落ち着いて受験できました。
私が希望の大学に無事合格できたのも、大好きなトフルの先生方、スタッフの皆さん、チューターさん、一緒に頑張ってきた友達のおかげです。本当にありがとうございました。
K.S.(東京都私立山脇学園高校):商学部私は受験には一番英語が重要だと思い、高1の時からトフルゼミナールに通いはじめました。通い始めたころは、テキストの予習・復習だけで精一杯だったのを良く覚えています。でも、その苦労した分、授業はちょっと緊張することもあったけど、毎回とても楽しく過ごすことができました。
そして何より、一番印象に残っているのは先生のすごさでした。長文に関することから始まり、今起きている時事に関することなど、次から次へと、どんどん話してくださいました。
しかもすごく詳しくてよくそんなことまで知っているなあと驚かされることばかりでした。そういうことも、思わぬところで役に立ち、またごさを感じました。そういう毎日の授業のつみ重ねが受験にもつながったのだと思います。
本当に先生方には感謝しています。ありがとうございました。
M.K.(東京都私立共立女子高校):教育学部少人数制なのが本当に良かったです。毎回授業ではあてられるので、予習を怠ることがなく授業に臨めました。また、先生方も一人一人を熱心に指導してくださって、英語の成績が伸びたのはトフルのおかげだと思っています。
勉強の仕方や進路で悩んだ時も、カウンセラーさんや、チューターさんが親身になって話しを聞いてくださって、受験という試練を乗り越えることができました。本当に皆様の熱いご指導のおかげです。ありがとうございました。
A.I.(東京都立西高校):国際教養学部私がトフルに入った最大の要因は、ずっと意識していた早稲田国際教養のコースがあることでした。英語の授業しかとっていませんでしたが、読解、文法、英作、リスニングと受講した4科目は充実していてどの授業も分かりやすく、先生の雰囲気も好きでした。
授業の予習・復習をするだけでも英語の勉強のリズムがつかめました。他にはテキストに出てくる単語はMY単語帳を作って必ず覚えるようにしていました。今思えば少しずつでもコンスタントな勉強が後で効いてきたのだと思います。
迎えた試験本番はとても緊張しましたが、だんだん順位の上がった模試や3冊たまったMY単語帳が自信となっていました。そして何よりトフルの問題が本番の英作文が的中したときはびっくりしつつ、心の中でガッツポーズでした。
発表を見たときは本当に信じられませんでしたが、今は感謝と喜びでいっぱいです。学校の行事も全力でやってこれて本当に満足です。トフルで学んだ英語を生かして大学でも頑張ります。
Y.N.(埼玉県私立西武学園文理高校):文学部私は、三年生の春から大手予備校をやめてトフルゼミナールに入りましたが、まずその授業の違いに驚きました。「長文読解というのは、一つ一つの文を構造分析し訳すことではない」と言う先生の下、量と質が上手く組み合わされた形で授業が進められました。
しかし何よりも、トフルに来て良かったと思うのは、先生方が沢山の知識を教えてくれたことです。長文のテーマから発展して色々な知識を教えてもらえたので、過去問や本番の入試のテーマにも通じ、「ああ、アレか」と多くの知識を基盤にして解くことができました。少人数でレベルも高かったので、難しくて楽しかったです。
A.T.(東京都私立富士見高校):政治経済学部本屋さんで、たまたまトフルゼミナールから出版している本を見つけて、トフルを知りました。その時、ちょうど予備校を探している時期だったので、これだ!と思いました。
私は、一方的に先生が広い教室で話すだけの授業は苦手だったので、大手の予備校は向かなかったのですが、トフルはとても少人数で密度の濃い授業を受けられて良かったです。教材のレベルが高く、教材を勉強するだけで英語力はかなり身につきました。私も、入学したときには、英語のトフルと思って入りましたが、これが、違う意味で裏切られ(笑)世界史、小論も良い授業で、安心してトフルに通うことができました。世界史もトフルのテキストしか使わなくなりました。本当に。授業の雰囲気も良くて、トフルに通うのがいつも楽しかったです。
私にとって、トフルは、塾でありながら、学校でもあり、家でもあったような感じです。進路で何度も迷いましたが、そのたびに先生も事務の方も親身になって相談にのってくださり、助けられました。特に、受験の直前は、精神的にも不安定でしたが、何も言わなくても先生は自分の気持ちを汲んでくださったりして、本当に強い味方でした。これは、大手の予備校では絶対に無理なので、トフルに決めてほんとに良かったと思います。
Y.O.(東京都私立頌栄女子学院高校):文化構想学部高2になりそろそろ受験のことも考えだしたときに目に入ったのがトフルでした。実は他の予備校を検討することもなくトフルに入ったのですが、本当に入ってよかったと思います。
自分の中で得意と思っていた英語でしたが、トフルの教材のレベルの高さに圧倒されました。そして集まっている生徒のレベルも高く、英語に対するやる気が出ました。先生はとても熱心で分かりやすく、懸命に授業を聞いて予習復習をくり返すことによって知らない間に成績がのびていました。英語が安定したことによって他の科目にも時間をかけることができました。
特に夏は自習室に開館から閉館までこもり勉強しました。少人数制であるところやアットホームな雰囲気のおかげで質問もしやすく、分からないところをどんどん消化することができました。
心配性な私をいつも励ましてくれた先生やスタッフのみなさんに感謝しています。おかげで第一志望に合格することができました。トフルに通って本当によかったです。
T.Y.(東京都私立安田学園高校):商学部僕は、高2の夏から友人に紹介されたのがきっかけでトフルゼミナールに通い始めました。授業を受けて、とても質の高い教材とクラスの友人に驚きました。
どうしても早稲田大学へ行きたかった私は予習・復習を繰り返し授業についていくことに必死でした。どの教科も素晴らしい先生方で、自分が英語以外もしっかり勉強すれば必ず合格できるという確信があったのでトフルゼミナールで全教科を受講し頑張りました。
3科目をバランス良く勉強し、小テストを受け、校内模試では常に満点を狙い、先生への質問は毎日でした。
辛くなる時もたくさんありましたが、先生、スタッフ、チューターの皆さんが相談にのってくださり、励ましてくれました。競い合い、支えあった仲間の存在も忘れられません。この合格はトフルで努力を続けた賜物です。本当に感謝しています。
N.M.(埼玉県私立浦和明の星女子高校):国際教養学部早稲田国際教養が第一志望で、いろいろな予備校を調べて英語に強く自分の第一志望大学学部の特別対策もあるとフルゼミナールを信頼してこの予備校に決めました。
実際に授業を受けてみて、レベルの高さに驚きながらもそれに触発され勉強に対してやる気も出ました。留学科のほうの授業も組み合わせ、ネイティブの先生に教えてもらうことで、自分の英語力も上がったと思うし、何よりも日本人の先生とはまた違った授業スタイルなのでとても楽しく、勉強しながら息抜きもできました。
古文、現代文、日本史も週に1日の授業でしたが、すばらしい先生方で自分の力を発揮することができました。午前は授業で、午後からは自習室にこもって閉館時間まで頑張りました。
毎日頑張れたことは何よりも一緒に頑張った仲間は私にとって不可欠でした。先生方、スタッフの方々とたくさんの人に支えられて頑張ってきた一年でした。
K.K.(愛知県立岡崎高校):国際教養学部授業が始まり、先生たちのレベルの高さに驚き、毎日予習と復習をひーひー言いながらこなして、授業についていくのがやっとでした。
トフルのアットホームな雰囲気が何よりも大好きで、事務の人たち、友達に出会って、私にとってトフルゼミナールは本当に“第二の家”という感じでした。最後の最後まで弱音を吐いていた私をいつも励ましてくれたスタッフには、ちょくちょく口では意地悪なことを言っていましたが、感謝の気持ちでいっぱいです。
M.S.(埼玉県私立川越東高校):教育学部私がこの塾に入ろうとしたのは現役のときに受験で大事なのは英語であると確信したからです。
トフルでの英語の授業というものは一人一人の先生方がそれぞれのやり方で定まった型にはまらずに教えていくといったもので私にとって毎時間毎時間がとても貴重であり楽しみでもありました。だからといって授業にばかりに頼り過ぎるのではなく自分でも予習、復習といったものを徹底して行いました。 そして社会や国語の授業というものも英語に負けず劣らずの個性派ぞろいの先生方が行うのでしっかりと力をつけていくことができました。しかし長い浪人生活は決して楽ばかりではありませんでした。いつも机に向かって黙々と勉強を行うということが苦になることもありました。そんなときは友人やチューターの人と話すことによって気分転換を行いました。
決して楽な浪人生活ではなかったけれど今私は本当この一年間トフルで頑張ってこれて良かったと思っています。
W.K.(東京都私立国学院久我山高校):教育学部トフルゼミナール入学当初から英語は得意科目ではありましたが、根拠のある解き方をしていなかったため成績は安定していませんでした。そこでトフルでの授業の取り組み方として、まず予習に時間をかけて自分なりの考えを持って授業に臨み、そして先生の細かな説明を聞くことで自分に足りなかった部分を補うことを繰り返しました。その結果、自然と長文の精読ができるようになって、答えも確信をもって出せるようになりました。
僕にとって弱点だった現代文ですが、トフルの授業を受けたことで、いかに自分が解き方を知らなかったのかが分かり、毎週授業を受けていくうちに正答を導き出せるようになっていきました。秋になり過去問を解き始めていくと、早稲田の難解な文章に悩まされましたが、とにかくこれまでに得た力で挑み続けました。
トフルゼミナールの授業は予習が必須なので、自分の弱点を克服するのに最適でした。僕はトフルのカリキュラムに合わせた勉強計画で効率よく勉強が出来たことが合格の最大の要因だったと思っています。
A.N.(東京都私立大妻多摩高校):法学部私がトフルゼミナールに出会ったのは高2の春。あまりに英語力が足りないため、さすがに予備校に通おうと思った時のことでした。大手の受験予備校ではきちんと自分の学習サポートを受けられるか不安だったので、少人数制予備校であるトフルゼミナールに入学を決めました。
当時の私の英語成績は、高校内では学年順位も真ん中より下で、早大法学部どころか受験自体を考えなくてはならない程の状況。今思い返しても悲惨でした。
トフル入学当初、少人数であることから、非常に丁寧な指導で分かり易く、また時には厳しく指導を受けることができました。私の英語に対する観念が変わり、学習法が確立したのはまさにこの入学直後からでした。ただ、最初はなかなか成績も伸びず、悔しい思いもありましたが、半年も経った頃から成績が伸び始め、最後は偏差値が25上がっていました。スタートが偏差値45だったということもありますが、それでも偏差値70まで上げることができたのは、やはりトフルで受けた指導の賜物だったと確信しています。
私は最終的に早稲田大学法学部に入学することができました。それは先生、スタッフが生徒一人一人に全力で指導してくれるトフルだったからこそ、この栄冠を掴めたのだと思っています。また、トフルの生徒は非常に前向きに勉強をする人ばかりなので教室の雰囲気も良く、モチベーションを保つことができました。「皆一緒に頑張ろう!」という空気は、私の受験勉強の支えになりました。
私の大学受験を大成功に導いてくれたトフルゼミナールに、私は深く感謝しています。
CLOSE

1882年に創立された最も歴史のある大学で、私立の最難関の一つです。人文科学、社会科学、自然科学の各分野にわたって13の学部を擁する総合大学で、40,000人以上の学生が学んでいます。
学部を超えて履修できるオープン科目があり、その内容も幅広く、自分の興味に合わせて学ぶことができる環境があります。
また、国際教養学部をはじめ7つの学部で英語学位プログラムを実施していることや、留学生の在籍者数は日本一(5,000人超)であることなど、進むグローバル教育も魅力の一つです。
様々なサークル活動が積極的に行われており、公認サークルだけで500以上あります。運動、芸術、文学、国際交流など、活動内容は様々です。
早稲田大学の建学の精神は、創設者大隈重信が述べたこの教旨の一文に集約されます。
「早稲田大学は学問の独立を全うし 学問の活用を効し 模範国民を造就するを以て 建学の本旨と為す 」(早稲田大学教旨)
権力や時勢に左右されず、学問を現実に生かせる進取の精神を持ち、豊かな人間性をもった地球市民を求めていると説明されています。
この理念に沿って、特に以下の3点を育むことが期待されています。
◆ 進取の精神に富んだ旺盛な知的好奇心とそれから導かれる独創性
◆ 自主独立の精神と他者への共感を育む豊かな感性
◆ 社会に貢献する強い意志を支える高い勉学意欲
(早稲田大学ホームページより)
13学部の枠を超えて学べる仕組みと、たくましい知性としなやかな感性を育てる教育プログラムがあります。
全学オープン科目制度があり、他学部の講義を自由に受講できたり、各学部が提供する科目のほかに、グローバルエデュケーションセンター(GEC)が提供する科目も自由に受講ができます。専門分野以外にも視野を広げることができるのは大きな魅力の一つと言えます。
*最新の入試情報や出願条件などは必ずご自身にて早稲田大のWebサイトでご確認ください。
早稲田大の一般選抜には、独自問題を使用する一般選抜と、共通テスト利用入試の2種類があります。
一般選抜は全学部で行われており、3教科いずれも独自問題を使用する学部と、共通テストを併用する学部とがあります。後者には国際教養学部、政治経済学部、スポーツ学部のほか、2025年度入試からは社会科学部と人間科学部も共通テスト併用となります。
また、国際教養学部、文学部、文化構想学部は英語4技能資格試験を利用した方式があります。
政治経済学部、法学部、社会科学、人間科学部、スポーツ科学部で利用されています。5教科が基本(スポーツ科学部を除く)となるため、特に国立大志望者の併願としてお勧めです。
※2027年度入試より国際教養学部でも共通テスト利用入試が開始されます。詳細はこちらをご参照ください。
一般選抜以外にも様々な選抜方式が用意されており、下記の他にも学校推薦型選抜(指定校推薦、北九州地域連携型推薦入試)もあります。
日本語で学位を修得するプログラムのための入試制度で、社会科学部、創造理工学部、先進理工学部、人間科学部、スポーツ科学部で実施されています。
法学部、商学部、文化構想学部、文学部、人間科学部、スポーツ科学部では地域探求・貢献入試が実施されています。
また、国際教養学部、文学部、文化構想学部は英語4技能資格試験を利用した方式があります。
英語で学位を取得できるプログラムのための入試制度で、政治経済学部、社会科学部、国際教養学部、文化構想学部、基幹理工学部、創造理工学部で実施されています。
国際教養学部を除く学部の日本語による学位取得プログラムに帰国生・外国学生を募集する入試制度です。
*帰国生入試については当校の帰国生専用ページをご参照ください。
https://tofl.jp/kikoku/index.php